|
|

私は、第二東京弁護士会に所属する弁護士です。
このサイトは、主に私が取り扱っている分野の法律や裁判に関する情報を提供することを目的としています
皆さんは、弁護士を頼まなければならないのは、どのようなときだとお考えでしょうか。テレビドラマで弁護士が登場するのは、殺人などの刑事事件が多いようですが、ほとんどの一般の市民にとって、刑事事件にかかわるのは、痴漢や窃盗、空き巣などの被害にあったときくらいなのではないでしょうか。
しかし、皆さんの周りにも、弁護士の助けを借りるべき場面が、案外、多くあります。たとえば、友人が貸したお金を返してくれない、夫から離婚を切り出された、保証人になった親戚の事業が失敗した、リストラされて生活費を借金したが返せない、会社でセクシュアル・ハラスメントを受けた、子どもが学校でケガをした、マンションを買ったが欠陥があった、などなど、数え上げたら切がありません。
困ったことがあったら、法律を使って解決できるかどうか、1度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
|
|
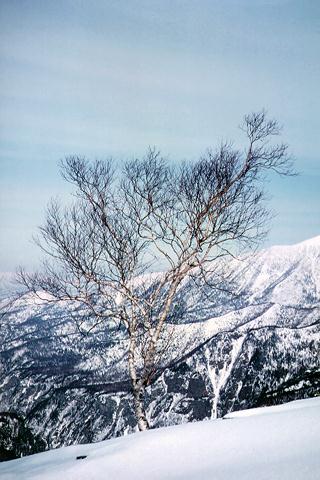 |
〒107-0052
東京都港区赤坂3-4-3
赤坂マカベビル9階
みのり総合法律事務所
TEL 03-3583-3226
FAX 03-3583-3227
|
弁護士会では、弁護士による各種の法律相談を低額な料金で行っています。
東京には、3つの弁護士会があり、各弁護士会が共同で複数の法律相談センターを設けています。詳しくは、弁護士会のッホームページを見て下さい。
第二東京弁護士会(私が所属している弁護士会です)、東京弁護士会、第一東京弁護士会
弁護士が、法的解決が可能であり、かつ、相応しいと判断した場合は、その事件に適した手続きを選んで助言してくれるはずです。多くの事件で、弁護士は、まず、対立する相手方と交渉することから始めます。交渉で決着が付かないからといって、すぐに裁判を起こすとは限りません。裁判以外にも、いろいろな手続きがあります。それらの手続きを紹介しましょう。
ただし、ここでは、利用可能なすべての手続の説明をしてあるわけではありませんし、法律の素人の方にも分かりやすいように、かなり簡素化して書きましたので、実際にこれらの手続きを利用する前に、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
家庭に関する事件は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停は、通常、40歳以上の男性1人、女性1人の2人の調停委員の前で行われます。
当事者(あなたと紛争の相手方)は、交互に、調停委員がいる調停室に入って、それぞれ、事件の経過や、解決方法に関する考え方を述べます。調停委員は、当事者の意見を調整して、合意するための手助けをします。
当事者の意見が一致したときは、家事審判官と呼ばれる裁判官、または家事調停官と呼ばれる弁護士が、合意の内容を書面にしてくれます。この書面は、調停調書と呼ばれ、書かれている合意の内容が、離婚や一定額の金銭の支払いなど具体的な場合は、確定判決と同じ効力があります。
いくら話し合っても、当事者の意見が一致しない場合は、調停は不成立になります。調停は、あくまでも当事者の自由な意思による合意を目指すもので、一定の解決方法を強制する手続きではありませんから、当事者が合意できなければ、不成立とならざるを得ないのです。
離婚調停や遺留分減殺請求など、一定の種類の事件は、調停が不成立になると、手続きはいったんそこで終了します。どうしても離婚したい当事者は、裁判を起こすしかありません。しかし、子どもの監護に関する事件(面接交渉や養育費、親権者・監護者の指定など)や、婚姻費用(生活費)の請求に関する事件など、調停が不成立になると「審判」と呼ばれる裁判に類似した手続きに自動的に移行する種類の事件もあります。
一般の民事事件は、簡易裁判所や地方裁判所に調停を申し立てることができます。調停のやり方は、家事調停とほとんど同じです。
調停の長所は、弁護士を頼まずに当事者が気軽に申し立てることができる点でしょう。なぜなら、調停はあくまで当事者が合意しなければ成立しない制度ですから、調停を起こしたからといって、裁判のように当事者の意思に反した結論を強制される心配がないからです。ですから、本来、「調停のやり方がまずかったから、権利を失った」とか、「義務を負わされた」ということはないはずです。もちろん、いわゆる「駆け引き」は別です。どういうことかというと、たとえば、調停で相手がずいぶん強気なので、有利な証拠を持っていて裁判に勝つ自信があるのだろうと思い、大幅に譲歩して調停を成立させたところ、後日、相手がはったりをきかせていただけであったことが判明した場合などです。
私が考える調停の短所は、特に弁護士が付いていない場合に顕著となります。それらは、次のようなものです。
① 裁判所という権威的な雰囲気がある場所で行われるため、当事者がその場の雰囲気や調停委員の意見に圧倒されてしまい、自由に意見を言えなくなってしまうことがある。
② 当事者は、自分にどんな権利があるのかを把握できず、十分な権利主張ができない可能性がある。
③ 当事者は、仮に裁判を起こした、あるいは裁判を起こされた場合に、結果の見込みがわからないため、必要以上の譲歩をしてしまう可能性がある。
④ 調停委員は、弁護士や不動産鑑定士、カウンセラーなど専門の資格を持つ者もいるが、多くは、事件に関係ある専門的が知識を持たない一般市民(素人)なので、必ずしも適切な助言を受けられるとは限らず、時間ばかりかかって何の成果も得られないという結果になることがある。
(訴えの提起)
民事裁判は、自分の主張を書いた「訴状」という書面を裁判所に提出することによって、起こします。
訴状には、ある法的効果が生じるために要件となる一定の事実を記載しなければなりません。これを「要件事実」といいます。
たとえば、あなたが友人に貸したお金を返してほしいとします。訴状には、あなた(原告)が、友人(被告)に対し、返してもらう約束の下に、いつ、いくらのお金を渡し、いつ返してもらう約束だったかをかを書かなければなりません。もし、利息を支払ってほしいのであれば、利息を支払う約束をしたことも書かなければなりません。
(被告の答弁)
被告は、「答弁書」という書面に、そういう約束があったのか、そのお金を渡してもらったのかなど、原告の言い分を認めるか認めないかを書きます。あるいは、そのお金はすでに返したとか、現金を返す代わりに高価な宝石を渡したとかいう事実があれば、反論としてこれを書きます。
それぞれの言い分は、証拠を提出して立証しなければなりません。裁判官は、証拠を調べて、どちらの言い分が真実なのかを判断して判決を下します。これが裁判というシステムです。
(和解の打診)
裁判の途中、それぞれの言い分が出そろった時点で、裁判官が当事者に、「和解」する気持ちがあるかどうか打診してくることがよくあります。「和解」とは、判決ではなく、当事者の合意によって事件を終わらせることです。先の例で言えば、あなたが友人に300万円を貸したので、300万円プラス利息を支払えという訴訟を起こしたとします。友人も300万円を借りたことは認めたものの、現金300万円をすぐに用意することができません。このような場合、裁判官は、友人が300万円を月10万円ずつの30回払いで支払い、あなたは利息分を負けてあげるという和解をしてはどうかと提案してくるかもしれません。あなたは、なぜ利息分を負けたり、30回の分割払いに同意したりしなければならないのか、初めは納得がいかないかもしれません。しかし、仮に勝訴判決をもらっても、お金がない相手からお金を取り立てるのは至難の業です。そうであるなら、たとえ分割払いでも、友人から300万円全額を返してもらえるならよいだろうというわけです。和解が成立すると、その内容は、和解調書という書面に記載されます。友人が、月10万円ずつの分割払いを怠った場合は、この和解調書に基づいて、給料差し押さえなどの強制執行をすることができます。
(証拠調べ)
和解が成立しないと、証拠調べの手続きに進みます。といっても、借用書など書面の証拠は、適宜提出していきますから、証拠調べというのは、通常、当事者や証人への尋問のことを意味します。当事者が尋問したいと望む人全員を裁判所に呼んで、尋問できるわけではありません。尋問は、当事者にとっても、裁判所にとっても、非常に時間と労力のかかる手続きですから、紛争の重要な部分に関する真に有益な知識ないし情報を持っていると思われる人を選んで、当事者は事前に証人申請し、裁判所がそれを必要と認めた場合に、尋問ができるのです。
尋問が済むと、通常、証拠調べは終わりです。
(再度、和解の打診)
証拠調べが終わった段階で、裁判官が再度、和解の提案をしてくることがよくあります。この時点では、弁護士はどのような判決になるかある程度の予測がつきます。といっても、たいていの場合は、①勝つ、②必ずしも勝つとは限らないが勝つ確立のほうが高い、③負ける、④必ずしも負けるとは限らないが負ける確立のほうが高い、⑤わからない、の5種類くらいでしょうか。(もっともこの予測が外れることもあります。)したがって、この時点では、判決を予測しながら和解の話し合いをすることになります。たとえば、あなたまたはあなたが雇った弁護士が、必ずしも勝つとは限らないが、勝つ確立のほうが高いと予測した場合、あなたは300万円以下での和解はしたくないと思うでしょう。しかし、負けるあるいは負ける確立のほうが高いと予測したら、100万円でもいいから、和解で確実に取り戻したいと思うかもしれません。
(判決)
和解が成立しなければ、判決となります。
判決は、送達(当事者が判決正本を受け取ること)から2週間経っても控訴されないと、確定します。つまり、それが国がこの事件に対して下した最終的な判断ということになるのです。
(判決後)
仮に、判決が、あなたの友人に300万円プラス利息を支払えと命じるものであったとしても、友人が任意に支払ってくれない場合、判決書を持っているからといって、無理やり友人の懐に手を入れて財布から金を抜き取ったり、友人の自宅に押しかけて金を払うまで居座ったりする権利が与えられるわけではありません。勝訴判決を生かすには、友人の銀行預金や給料を差し押さるなどして、判決で認められた権利を実現する必要があります。これは、「強制執行」といって、裁判とは別の手続きです。
(弁護士の役割)
弁護士を頼まずに民事裁判を起こす人もいますが、裁判を行うにはかなり専門的な法律知識を必要としますので、やはり弁護士に頼むことをお勧めします。ただし、簡易裁判所で行われる比較的少額な事件では、弁護士を頼むと費用倒れになってしまう場合もあり、また、「司法法員」と呼ばれる弁護士が当事者が適切な解決に至るよう和解の仲介をしてくれるので、弁護士を頼まずに裁判を起こす人も多くいるようです。
弁護士会が行う「あっせん」とは、紛争の当事者が弁護士(あっせん人)に言い分を聞いてもらい、、あっせん人の助言を受けながら和解による合意を目指す手続きです。裁判所で行っている調停と同じような手続きを、弁護士会の弁護士が調停委員となって行うものと考えればよいでしょう。話し合いに法律の専門家である弁護士が常に関与する点で、裁判所の調停より勝っているといえるかもしれません。
「仲裁」という言葉は、ケンカの仲裁くらいしか聞いたことがないかもしれません。しかし、これは立派な法律用語です。「仲裁」とは、紛争の当事者が、ある人または機関を指定して、その人またはその機関が選んだ人に事件を判断してもらうことにして、その人の判断に従うと約束することです。仲裁の長所は、裁判と違って公開の法廷で行うわけではないので、当事者のプライバシーが守られることです。
あっせん・仲裁についての詳細は、日本弁護士連合会のホームページまたは第二東京弁護士会のホームページをご覧下さい。

